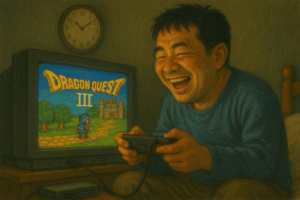アリョーシャの涙と、理想家の覚悟 ―『カラマーゾフの兄弟・第2部』を読んで
「カラマーゾフの兄弟」を読み始めてから2年。
ついに第2部の、あの衝撃的な“ゾシマ長老の章”に到達しました。
読み終えてページを閉じたあと、胸の奥がざわざわし続けて、なかなか日常に戻れません。
尊敬が一瞬で侮蔑に変わる、人間の心の揺れ。
そしてその混乱の中で、アリョーシャが再び立ち上がり、
揺るぎない信念を取り戻していく姿。
この流れを読んでいて、ふとペアレント・トレーニング(ABA)で学ぶ
「行動は感情に左右されやすいけれど、“選び直す力”は誰にでもある」
という考え方が頭に浮かびました。
人は、嫉妬や不安で簡単に態度を変えてしまう。
でも同時に、絶望を味わっても、もう一度“こうありたい”という理想を選び直すこともできる。
アリョーシャが大地を抱きしめて涙するシーンは、まるで「信じたいものを、自分で選び直す瞬間」の象徴のようで、読んでいて胸が熱くなりました。
200年読み継がれてきた理由が、いま少しだけ分かった気がします。
📚ゾシマ長老とは?
この物語の主人公・アリョーシャが深く敬愛する修道院の長老。
慈愛と柔らかな智慧を持ち、訪れる者の痛みに寄り添う、まさに“聖人”のような存在です。
しかし、死後に起こる“ある変化”をきっかけに、長老への評価は一転。
尊敬は冷え、侮蔑に近い態度さえ起こる……この落差が胸に刺さります。
📚尊敬の裏に潜む嫉妬心
ゾシマ長老に対して態度を急変させる人々の姿は、まさに“どんでん返し”。
でも読み進めるほどに、
「ああ、こういうことって現実にもあるよな……」
と思わされました。
たとえば総理大臣。
就任直後は賞賛されても、数ヶ月もしないうちに風向きが変わり、批判が吹き荒れる。
もちろん政策への不満もあるでしょうけれど、その背後には
「羨望」「嫉妬」「自分との差」
といった感情も、少なからず混じっている気がします。
📚成功こそリスク
私は以前、経営コンサルタントをしていました。
様々な企業や社長さんと接するなかで、痛感したことがあります。
それは、
「成功そのものが、次のリスクを誘ってしまう」
ということ。
努力に努力を重ねて成功した会社ほど、
ちょっとした慢心や油断で、足場が崩れてしまうことがある。
実際、私も30代の成功に寄りかかり過ぎて、40代で痛い失敗をしました。
職を失い、すべてを一から見直すことになったので、偉そうなことは何も言えません。
📚アリョーシャが得た揺るぎない信念とは?
長老の死後に起こった“変化”と、ひとの心の残酷さに触れ、アリョーシャは絶望し、信念を失いかけます。
しかし、物語の終盤、彼は大地を抱きしめ、涙を流しながら、揺るぎない信仰心を取り戻します。
どうして彼はそこまで強くなれたのか……?
その理由は、まだ明確には語られていません。
この先の展開で描かれるのでしょうか・・・?
とても楽しみです。
🎸スピッツ『ビギナー』に見る“理想家という生き方”
スピッツの『ビギナー』は、軽やかなメロディとは裏腹に、
「理想を掲げて生きること」への切実さがぎゅっと詰まった歌です。
理想を言葉にするのは簡単です。
「正しさ」や「優しさ」や「誠実さ」を目指すのは立派だし、誰もが憧れます。
でも実際に、それを毎日の生活の中で一つひとつ選び取っていくのは、とんでもなく大変。
周りから笑われたり、裏切られたり、自分の弱さに負けそうになったり、どうしても折れそうなことがある。
それでも、何度くじけても、
「もう一度、同じ理想を叫び直す」
そんな姿勢そのものが、“理想家の覚悟”なのだと思います。
ゾシマ長老が示したもの、アリョーシャが受け取ったものも、そういった覚悟なのかもしれません。
スピッツの「ビギナー」はこんな一節で締め括られます。
『だけど追いかける 君に届くまで
慣れないフォームで走り続けるよ
霞む視界に目を凝らせ』
「ビギナー」を聴きながら、
大地を抱きしめて涙したアリョーシャも、こんな気持ちだったのかも?と思いました。
・スピッツ『シロクマ/ビギナー』
ーーーーーーーー
📚最近のロシア文学は読みやすい
「カラマーゾフの兄弟」はとにかく登場人物が多く、
カタカナのロシア名になかなか馴染めず、
私は第一部だけで2年もかかってしまいました。

でも光文社文庫版には、登場人物紹介が書かれた栞が付いていて、
これを確認しながら読むと、理解が一気に深まります。
控えめだけれど、とても大きな読者サポートだと思います。
📚カラマーゾフの兄弟2