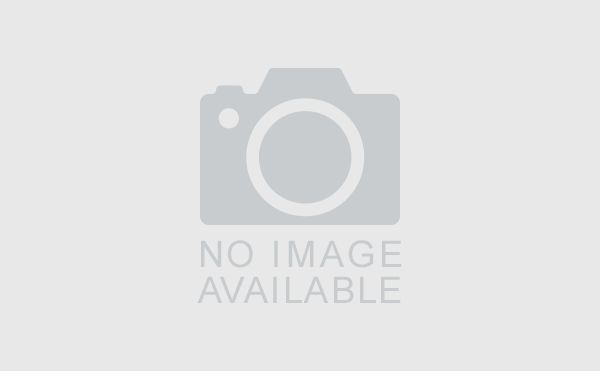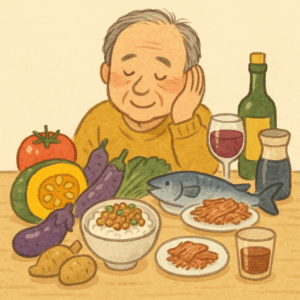『家族の舟』で学ぶペアトレ15のヒント〈6〉行動の4つの機能とは?
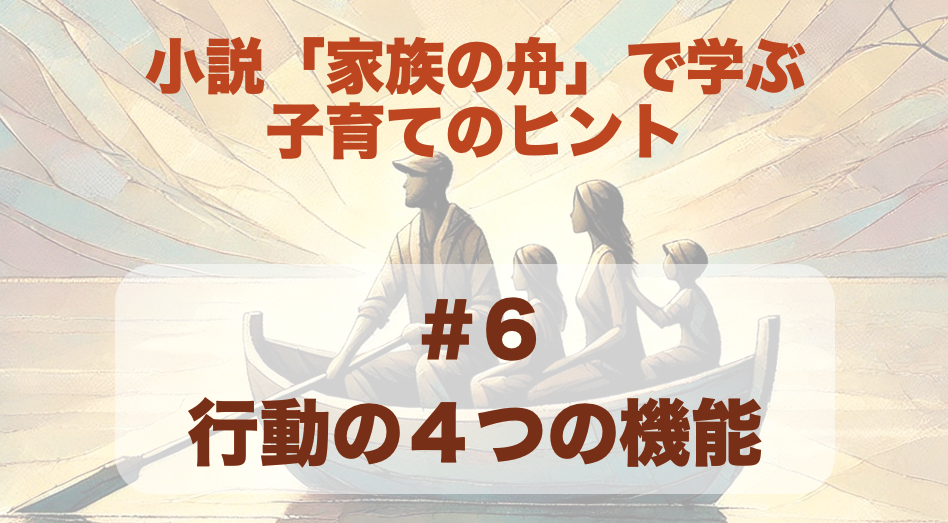
「親から『怒られる』とか『説教される』といったリアクションは、
お子さんにとって、必ずしも『不快』であるとは限らないんですよ」
——水谷インストラクターの言葉第11章 ペアトレ講座・二回目 より
■ なぜ、その子は“わざと怒らせるようなこと”をするのか?
親として、支援者として、
「なんでこんなことするの?」「どうしてわざわざ怒られるようなことを…?」
そう思ったことはありませんか?
ペアレント・トレーニングでは、こうした**“困った行動”にもちゃんと理由があると考えます。
それが、「行動の4つの機能」**という考え方です。
■ 行動には4つの“目的”がある
-
注目を得るため(注意喚起機能)
→ 例:「かまってほしくて騒ぐ」 -
物や活動を得るため(具体的報酬)
→ 例:「ゲームしたくて嘘をつく」 -
嫌なことから逃れるため(回避)
→ 例:「宿題が嫌で寝たふりをする」 -
自動的な快感や安心のため(自己刺激)
→ 例:「手を振ったり独り言を言うことで落ち着く」
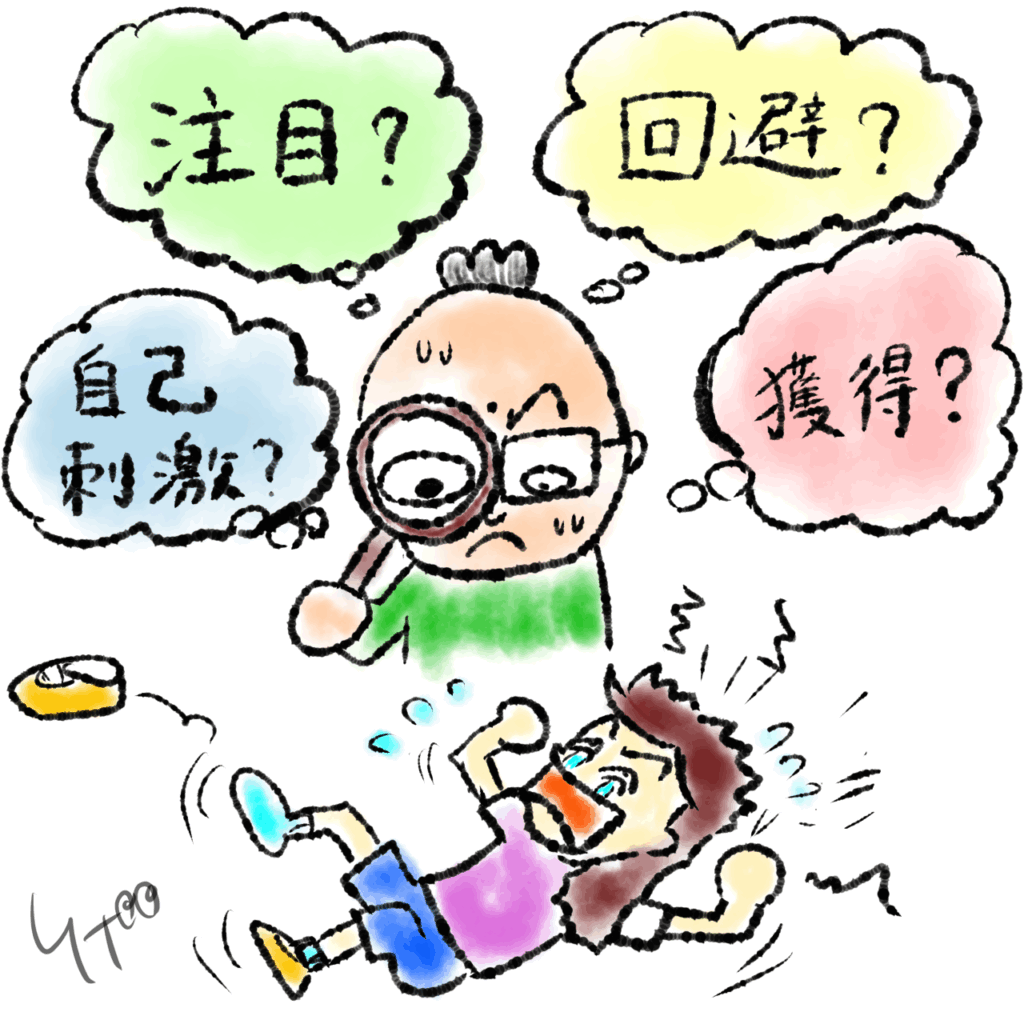
■ 「怒られてもいいから注目してほしい」が一番厄介
水谷インストラクターが言うように、
“怒られること”ですら、子どもにとっては“親の関心がもらえる”という報酬になってしまうことがあります。
たとえば、親が普段忙しくて構ってくれない。
でも、悪さをすれば怒られる。
→「だったら怒られてでもいいから、こっちを見てほしい」と子どもは無意識に選んでしまう。
■ 大切なのは、「行動そのもの」ではなく「背景を推理する」こと
“問題行動”を見たとき、「叱る」よりも先に考えてみてください。
-
これは、誰かの気を引きたいのか?
-
なにかを避けたいのか?
-
単に自分の心を落ち着けるためなのか?
背景の機能を見抜くことが、適切な対応につながります。
■ 行動の意味がわかると、子どもが見違えて見える
「悪い子」ではなく、「かまってほしい子」
「怠けている」ではなく、「どうしたらいいか分からない」
行動の裏にある“心の声”を聴けるようになると、
叱る回数は減り、関係性そのものが変わっていきます。
✍️しげのひとこと
子どもは、行動でしか「助けて」って言えないときがある。
【ペアトレをテーマにした小説を出版します】
うつ病、不登校、家庭内暴力。
沈没しかけた家族に、一つの航路が生まれた。
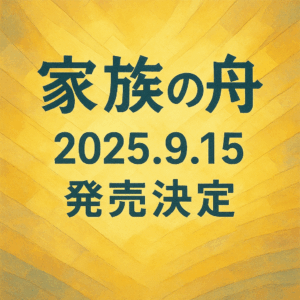
しげの実体験をもとにした小説「家族の舟」
2025年9月15日 「私」物語化計画より出版