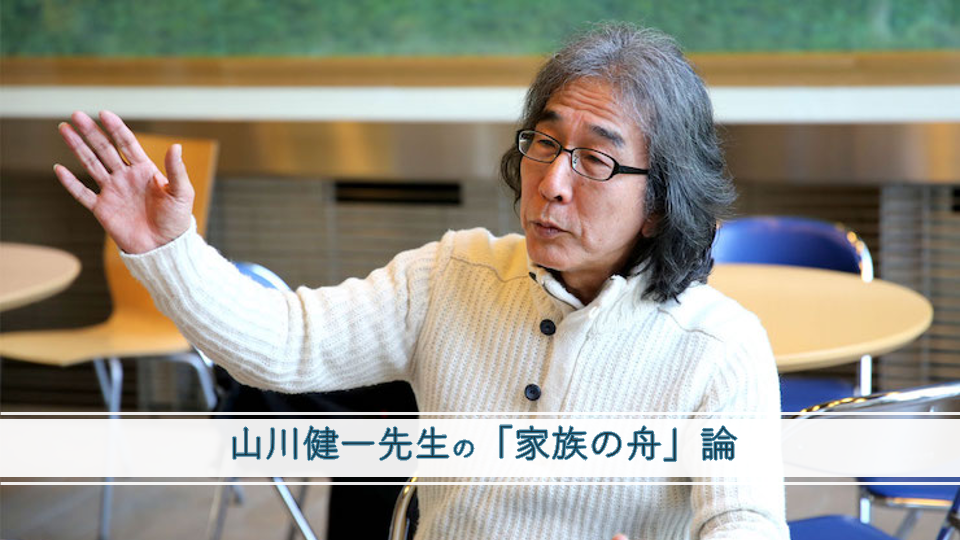
(※以下の論文は、山川健一先生主宰「私」物語化計画の会員向け講義文です。山川先生に許可をいただいて、ご紹介させていただきます。)
「家族の舟」論 01 荒れた海の航海
今週から何回かにかけて、西山仁胤氏の「家族の舟〜亜希のペアレント・トレーニング〜」論を書く。物語化計画ブックスで、9月15日に刊行予定の長編小説だ。
小説というものは、実はマンツーマンの指導が1番良い。大学教員をやった経験から、例えば100人の学生にマンツーマン指導を行うのは不可能なので、物語論というロジックを自分なりに構築し、作品執筆のためのアドバイスを行う技術を磨いてきた。物語化計画での指導も、これに準じている。
だが、それでもなお、本来なら作品を間に挟んで面と向かい合い指導していく方法がもっとも良いのは明らかである。
文学というものは概念だが、小説は作品個々の概念とともに、肉体を兼ね備えている。そこに魅力がある。このいわば文学的な肉体について指導するのは、なかなか難しいのだ。
そこで思いついたのが、この連載である。同じ物語化計画の仲間である西山さんが、どのようにこの物語を書いていったのか、その過程を紹介することで、小説の肉体というものを、皆さんにも見て欲しいと思うのだ。「家族の舟」は9月に刊行予定で、実際に皆さんが読めるのは少し先になるが、肝心な箇所は引用もさせてもらうつもりだ。つまりネタバレも含まれることになる。
【Amazonに掲載予定の紹介文】
この長編は400字詰め原稿用紙で500枚に及ぶ長編だが、少しも長さを感じさせない。ハラハラドキドキ、ストーリーに引き込まれていく。
ジェットコースター・ストーリーと言っていい。
ストーリーに引き込む技術は、小説を書く上でもっとも大切な技術の一つであるが、西山仁胤はこの最初に書いた小説でそいつを実現している。
しかもこの長編は、リアルで、感動的で、読む者の魂を揺さぶる力を持っている。
長い作品の中に決定的な力学の転換、プロットポイントが複数仕掛けられている。ぴこ蔵師匠が提唱しているドンデン返しであるが、これは物語の魅力や興味を引くために配置するものだから、少し大袈裟にした方がいい──と僕はアドバイスした。
これは、読者が「先を読みたい」と思えるための「罠」なのだ。
概要をくどくど説明するのではなく、Amazonに掲載予定の紹介文を引用しよう。
《●キャッチコピー
沈没寸前の家族に、ひとつの航路が生まれる。
●説明文
父はうつ病で仕事を失い、社会にも家庭にも居場所を無くして死にたいと願った。高校生の長女は怒りと不安を家庭内暴力という形で爆発させた。
自閉症と知的な遅れのある小学生の次女は不登校に。
そして母は看護師という激務に耐えながら、なんとか家族を繋ぎ止めようと踏ん張った。
そんな崩壊寸前の四人家族がたどり着いたのが、「ペアレント・トレーニング(ペアトレ)」だった──。
この物語は、実在する家族の姿をもとに、家族の“やり直し”を描いたフィクションです。何かを失って初めて、自分が何を見てこなかったかに気づく。変わらなければいけないのは、子どもではなく、まず“親”なのかもしれない。
子育てに悩む人、理想通りの親になれず自分を責めすぎてしまう人。家族という言葉に、もどかしさと憧れを同時に抱いているすべての人に、この物語を届けたい。
著者自身の経験に基づく、静かで力強い“家族の再生”の物語。読み終えたとき、あなたの中の「親」「子ども」「家族」という言葉の意味が、少しだけ変わっているかもしれません。
子育てに悩むすべての人へ。
家庭の再生は、“知識”や“正しさ”ではなく、“やり直す勇気”から始まる──。
●著者プロフィール
しげ(西山 仁胤/にしやま しげかず)
1974年、広島市生まれ。現在、放課後等児童デイサービス「きらり」で働く保育士。
2013年、うつ病を発症し、当時の仕事であった経営コンサルタント業を廃業。主治医の勧めで精神障害者手帳3級を取得。
2018年、娘が自閉症と知的の遅れがあるとの診断を受ける。
2023年、山川健一主宰『「私」物語化計画』に入会。山川氏の指導を受けながら、本作を完成させる。》
【書き出しで提示される欠落】
小説を書く上で大切なのは書き出し部分であるが、作品の冒頭でその世界の「欠落」を提示しなければならない。これは基本である。
しかも「欠落」を描く際、可能な限りその輪郭をくっきりと描くべきである。「欠落」を埋めるために主人公は旅立つ。ナラトロジーで言うセパレーションであるが、その輪郭がはっきりしているからこそ、物語の全体が力強く動き続けるのだ。「家族の舟」はこの最初のハードルをいかに乗り越えたか?
プロローグの一部を引用する。
《プロローグ 2023年
部屋は穏やかで暖かい朝の光に満たされている。新しい週の始まり、月曜日だ。大野浩司は穏やかな笑みを浮かべて、キッチンのシンクに180cmの長身をかがめ、食器を洗っている。蛇口から流れ出る水の音と、カチャカチャと食器同士が触れ合う音が小気味よく響いている。左手にあるガスコンロの横の小窓からは明るい朝日が差し込んでいる。小窓の横のラックに置かれたトースターの中では、ニクロム線ヒーターがオレンジ色の光を放ち、その下で食パンがゆっくりときつね色に色づき始めている。そのパンが焼ける甘くて柔らかい香りが漂ってくる。
蛇口を捻って水を出し、浩司は食器についた泡を洗い流しながら、その芳しい小麦の香りを深く吸い込む。皿についたバターを泡のついたスポンジでこすりながら、彼は自分の周りを満たしている幸せな空気を噛み締めていた。全てがうまくいっている。彼はそう実感していた。真冬の水道水の手の甲を刺すような、冷たさ通り越して痛みに近い刺激さえも心地いい。それくらい、彼の心は満たされていた。
「お父さん、カッコいいね」
突然の背後から声に浩司は驚き、慌てて水道の蛇口を止めてから振り向く。声の主は十六歳になる次女の亜希だ。
「そ、そう?」
浩司は娘の方を振り向きながらエプロンで手を拭き、下を向いて自分の服装を見た。今朝も、五、六年前に無印良品で買ったLサイズの茶色の冬用パジャマを着ている。何度も洗濯したので、色褪せてヨレヨレで毛玉だらけである。しかも買った時より随分と太ってしまい、お腹とお尻の布地がパンパンではち切れそうだ。早くXLサイズのパジャマを買わないといけないと思いながら、買いに行くのが面倒でそのまま着続けている。
「カッコいいかな?」
浩司はバツが悪そうに頭を掻いた。寝癖でボサボサの頭髪は、生え際と頭頂部がだいぶ薄くなった。毛の少なくなった部分を触ると、頭皮の感触が指先にダイレクトに伝わり、切なくなる。来年で五十歳。年相応に老け込んだことを自覚している。それでも、
「うん、カッコいいよ」
亜希は屈託ない笑顔で繰り返し、お気に入りのアンパンマンのマグカップに入ったココアを一口飲んだ。彼女は天然パーマの強い髪を、ポニーテールにして後ろで束ね、前髪を黒いピンで止めていた。そして学校の制服である長袖の白いポロシャツと、その上から紺色と濃い緑のチェック柄のジャンパースカートを着ている。
亜希は広島市立広島特別支援学校の高等部に通う一年生だ。彼女は『特別』な『支援』を必要とする子ども。つまり、障害児である。『自閉症と知的な遅れ』。それが亜希についた診断名である。知能指数は同級生の半分程度。年齢は十六歳だが、八歳程度の能力しかない。
窓から差し込む柔らかい初冬の光の中、美味しそうに微笑みながらココアを飲む娘の姿に、自然と浩司の口元はほころんだ。そして、かつての地獄のような日々は夢のようだ、と感慨に浸った。
今から五年前、当時小学五年生だった亜希は不登校だった。毎朝、「学校に行け!」という浩司の怒号と、「行きたくない!」と亜希が泣き叫ぶ声が、カーテンを閉め切った薄暗い寝室に響いた。当時の亜希は着替えることも嫌がり、何日も同じパジャマ姿で過ごしていた。風呂に入ることも嫌がって、いつも髪はボサボサで油っぽくフケだらけ。顔は常に青白く、浩司と目を合わせないように常に下を向いていた。当時の家の中の空気は常に暗く、澱んでいた。あの頃に比べて、この朝の空気の、なんと清々しいことか。浩司は腰に手を当てて胸を逸らし、鼻から大きく息を吸い込んだ。焼き上がった食パンの香ばしい匂いと、亜希が飲むココアの甘い香りが混じり合って、心地よく鼻腔をくすぐる。窓からは明るく澄んだ朝の光が差し込んでいる。浩司は、胸の奥から溢れる幸福感に、さらに頬が緩んでしまうのを、どうしても止められなかった。
亜希は知能と同様に、体の成長も遅かった。身長は140cmで、体重は38kgである。見た目にも小学三年生くらいにしか見えない。趣味や興味も、その知能と体格と比例して幼い。一般的な十六歳が、流行のファッションや歌手やアイドルを追いかけ、異性や恋愛に興味津々な中、亜希は未だにリカちゃん人形と、ドラえもんと、クレヨンしんちゃんに夢中である。同級生が思春期を迎えて親に反抗している中、亜希はいまだに幼児のような屈託のなさで、両親と姉の凉香にまとわりついてくる。買い物には必ずついてくるし、中学入学と同時に亜希専用の子ども部屋を与えたけれど、そこで一人で過ごすことは全くない。常にリビングにいて家族の誰かと一緒に過ごす。そして夜寝る時は、「一人で寝るのは怖い」と言って、いまだに浩司と母親の美佳子の間に挟まれて川の字になって寝る。
「でも、デブで、ハゲで、オッサンだよ? カッコいいかね?」
浩司は照れて亜希にそう問いかけながら、マグカップにインスタントコーヒーの粉を入れ、ヤカンに沸いたお湯を注いで、スプーンで掻き回した。
「うん! カッコいいよ!」
亜希は即座に答え、そしてニッコリと笑った。その細めた目の周りはいつもアトピー性皮膚炎の影響で薄いピンク色に充血し、皮膚がささくれだっている。整った顔立ちをしている美佳子に似て鼻筋は通っているが、顎が少しずれており、そのせいで口が右にひん曲がっているように見える。口を開けて笑うと、ガタガタで隙間だらけの歯並びが姿を現す。上の前歯の右隣の歯だけ、なぜか異様に小さく、歯茎からほんの三ミリほどしか顔を覗かせていない。そのせいで、笑うとそこだけ歯が抜けている。浩司はその笑顔を見るたび、子どもの頃に夢中になって読んだ漫画「ドクタースランプ」に出てきたガッチャンを思い出す。
亜希の笑顔は、世間一般の美的基準で言えば、決して美しくないし、可愛くはないだろう。しかし浩司にとっては、朝の日差しの中の、ガッチャンのように屈託なく笑う亜希の微笑みは、何事にも変えがたい愛おしいものなのであった。》
【Soul Survivor】
何度読んでも、このプロローグは魅力的である。次女の亜希の小さく痩せた肉体が読者に向かって立ち上がってくる。
亜希はイノセンスの象徴なのである。
だが同時に、デブでハゲでオッサンの主人公が潜り抜けなければならなかった嵐の激しさを、読者は想像することになる。
プロローグは最初は独立した短編で、何度か改稿してこの形になったのだが、最初から亜希は登場した。物語の登場人物として、亜希はあまりにも魅力的である。そして、娘に注がれる父親である主人公の愛に溢れた視線。
これは長編小説にすべきだと僕は確信した。
だがそのためには、作家自身は長く苦しい旅を続けなければならない。西山仁胤は嵐が猛り狂うその航海を完遂することができるだろうか?
そしてまた、「文学」の名のもとに僕がそんな作業を彼に強いていいのだろうか?
下手すると、作家が航海の途中で海に沈んでしまうかもしれないのだ。
詩人のリルケがこんな意味のことを言っている。
「詩を書くことは、深い海に潜って真珠をとってくるようなものだ。深く潜れば潜るほど、大粒の美しい真珠を手に入れることができる。しかし、あまりにも深く潜りすぎると命を落とすことになる」
僕は長らく文学生活を続けてきたから、周囲に小説を書きたいという友人が多かった。成功した人も多いが、中には深い海に沈んでしまった人もいる。
僕は悩みに悩んだ。大粒の美しい真珠に目が眩んだ文学の悪魔と化していたのかもしれない。
ローリング・ストーンズにSoul Survivorという曲がある。「海が荒れている時、航海はたいへんだ。俺はおまえの愛の中で溺れそうだ。おまえはクルーの喉を切り裂いた。魂の生存者、俺は魂の生存者」という歌だ。
ある時、一つ大きく息を吸い、それを吐き出して僕は決意した。ジャンボ(僕は彼をそう呼んでいる)に書かせよう、彼なら大丈夫だろう。俺は作品が完成するまで根気よく付き合おう──と。
彼はSoul Survivor、魂の生存者になってくれるはずだ。
西山仁胤は、ジャンボ亭ばずーかは、しげは、荒れている海を乗り切ったよ。なあ、僕にも言わせてほしい。デブで、ハゲで、オッサンでも、カッコいいよ!
(続く)
「家族の舟」論02 夏の朝焼けのような予兆
【希望をつなぐことができない日本】
マンションの3階にあるテラスの向こうの空が、朝焼けに染まっている。近くの公園のけやきの葉が風にざわめき、空の端が濃い朱色に染まり、そいつが刻々と暗闇の中で薄い青に溶けていく。
東京は長らく雨の日が続いたが、今日は晴れるのだろう。
これは何かの予兆だろうか、と僕は考える。
世界も日本も、人間の世界は混乱を極めているというのに、空は今日も高い。人類という種は、この地球にいない方がいいのかもしれない。本気でそんなことを考える。
日本には今や外国人が溢れ、あと数年もすれば新疆ウイグル自治区のような有様になりかねないと言う人がいる。そうかもな、と僕も半ば諦めの気分で嘆息する。そうすると、テラスの向こうの朝焼けは、滅びゆく日本の予兆なのだ。
日本とは何だろうか?
私見によれば、「日本」の大きな部分を日本語が担っている。日本の言語こそが日本という国なのである。
そして小説は日本語によって記される、ほぼ最高峰の表現である。
僕らが小説を書くという困難で厄介な仕事を続けているのは、たとえそれがカタカナが多用されるロック小説であろうとも、日本を支えていくためなのではないだろうか?
自分の日本語を鍛え、小説にそれを活かす。それは自分の中の祖国を守るということだ。
この連載で一度も触れていないことを書く。
小説──物語の冒頭には「欠落」がなければならない。それはナラトロジーの基本である。だがそれだけでは不十分なのだ。
小説全体の「予兆」が提示されていなければならい。予兆を書くことに類い稀な才能を発揮したのは三島由紀夫だった。予兆が書かれた瞬間に、その小説は一気に緊張感を増す。
三島由紀夫は東京・市ケ谷の自衛隊駐屯地で割腹、自決する4カ月前に、産経新聞に寄稿したエッセイの中でこんなふうに警告している。
《二十五年間に希望を一つ一つ失つて、もはや行き着く先が見えてしまつたやうな今日では、その幾多の希望がいかに空疎で、いかに俗悪で、しかも希望に要したエネルギーがいかに厖大であつたかに唖然とする。これだけのエネルギーを絶望に使つてゐたら、もう少しどうにかなつてゐたのではないか。
私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行つたら「日本」はなくなつてしまうのではないかといふ感を日ましに深くする。日本はなくなつて、その代はりに、無機的な、からつぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであらう。それでもいいと思つてゐる人たちと、私は口をきく気にもなれなくなつてゐるのである。》三島由紀夫「果たし得てゐない約束――私の中の二十五年」
今の日本は富裕ではない。国民は貧困に喘いでいる。この国はもはや経済大国とは言えないのである。
三島由紀夫の死こそは、今の日本の予兆だったのかもしれない。
コメ騒動の裏でしれっと自公立民が閣議決定していた「年金制度改革法案」。「2,336万円もらえるはずが365万円に」なる。遺族年金の給付を大幅カットするのだ。
夫に先立たれた女性達は生きていけない。自公立民が束になって日本人を潰しに来ている。
政府は中国人留学生に1,000万円支給していた。その一方、日本人の学生は奨学金という名のローンに苦しめられている。
消費税は社会保障の財源ではないことに、国民は気づいてしまった。トヨタ自動車など輸出大企業20社が国から還付された消費税還付金額が、1兆9千億円に達することが分かった。トランプ大統領が、日本は消費税を廃止しろと言っている。
もはや暴動が起きても不思議ではない状況だろう。
日本が滅亡する予兆が、あちこちでろている。
三島由紀夫の話の後だとジャンボが萎縮してしまいそうだが、「家族の舟〜亜希のペアレント・トレーニング〜 」のプロローグには鮮やかな「予兆」が書き記されている。先週引用した箇所の後の部分を紹介しよう。
【プロローグ後半】
《浩司はトーストの最後の一口を口に放り込むと、「ごちそうさまでした」と皿に向かって頭を下げた。その皿をシンクに片付けると、今度は朝刊をテーブルの上に広げた。まずは折り込みチラシをチェックする。近所のスーパーの特売情報を確認するためだ。「おっ?」近所のスーパーのパンの特売デーの見出しに、浩司は身を乗り出した。このスーパーは店内にパン工房があり、いつでも焼きたての美味しいパンを食べられることで評判だ。美佳子はここのウィンナーパンが大好物なので、これから夜勤明けで帰ってくる妻のために買っておこうと、浩司は思った。そして、スマホを手に取ると、メモのアプリを立ち上げて「ウィンナーパン」と入力した。さらに他のチラシもチェックしていく。結婚相談サービスの広告が目に入った。それを見て浩司は、美佳子が照れくさそうに言った言葉を思い出した。
「浩ちゃんみたいな人が、理想の結婚相手なんだって」
一週間ほど前、仕事から帰ってきた美佳子は、こんな話を聞かせてくれた。
美佳子は広島市内の総合病院で看護師をしている。昼食休憩の時に、独身の若い看護師さん達が理想の結婚相手について話していた。美佳子が横でそれを聞きながら弁当を食べていると、その中の一人が、「私、大野さんの旦那さんみたいな人がいい」と言い始め、他の独身の看護師さん達も「私も!」と、次々と賛同してくれたというのである。美佳子が驚いて理由を聞くと、「炊事、洗濯、料理、家事は全てできるし、毎日、職場まで車で送り迎えしてくれるから」とのことだった。その若い看護師さん達の発言には、彼女たちの上司である美佳子のご機嫌取りの意図もあったのだろうと浩司は思う。だが、そうだとしても嬉しかった。直接会ったことはないし、今後も会うこともないだろうが、その若い看護師さん達に「理想の結婚相手」と言ってもらえたことで、彼の自己肯定感は大幅に上昇した。ふとチラシから顔を上げた時、食器棚のガラスに映った自分の顔が目に入った。なるほどこれが「鼻の下が伸びる」というやつか、と感心したくなるくらい、顔面の肉全体がとろけて落ちそうなほどニヤけていた。そんなだらしない自分の顔に、浩司はおかしくなって、一人で声を立てて笑った。
浩司はチラシを全て見終わり、新聞を手に取った。テレビ欄をチェックしてから一枚めくって社会面を開く。娘を虐待死させた父親の裁判の記事が彼の目に飛び込んできた。頬が冷たくなり、固く強張る。朝から嫌な気分になりたくない。浩司はそう考えて、新聞を閉じようとした。しかし、できなかった。きっと書かれていることは、他人事ではない。この記事から逃げてはいけない。そんな気がした。浩司は覚悟を決め、短く息を吐き出した。そして、少し下腹に力を入れて、記事を読んだ。
…X県の会社員・容疑者Z (四十四歳)は、小学三年生の娘が言うことを聞かないことに腹を立て、「躾」と称して日常的に暴言、暴力、体罰を加えていた。そしてある晩、子どもが泣き止まないことに腹を立て、風呂場で娘の体に熱湯をかけ、全身に大火傷を負わせた。その後、娘をそのまま放置し、死なせてしまった…。
浩司は居た堪れなくなって、新聞を閉じた。彼の耳の奥に、幼い頃の凉香と亜希の、泣き声が蘇る。浩司はそれを払いのけるように首を振って、目を固く閉じた。すると今度は瞼の裏に、凉香と亜希が、大粒の涙を流す顔が浮びあがる。その映像に、自分の怒号が被さる。
「うっせえな! 泣くな! クソガキ!」
さらに子どもたちの泣き声は大きくなる。
「ごめんなさい! ごめんなさい! もうしません! お父さん、ごめんなさい!」
凉香と亜希はしゃくりあげながら、必死に浩司に懇願する。
「もうやめて! 許してあげて!」
美佳子も泣きながら、浩司の右腕に縋りついてくる。「うるさい!」と浩司は美佳子の細い腕を払いのけ、
「黙れボケ! 許して欲しければ、泣くな!」
さらに大きな声で、子どもたちを怒鳴りつける。
浩司は、激しく首を振って、忌まわしい記憶を頭から追い出そうとした。そして自分の胸の中に渦巻く、真っ黒なヘドロのような重苦しい感情を振り払おうと、冷めたコーヒーを一気に喉に流し込んだ。むせて咳き込み、ほとんどを閉じた新聞とテーブルの上に吐き出してしまった。ティッシュペーパーを何枚も出して、それを拭いた。
あらかた拭き終わると、茶色く汚れたティッシュの塊を、テーブルの上に放り出した。
「…何が、理想の結婚相手だ…」
浩司は両肘をテーブルにつき、頭を抱えた。
俺はひどい父親だ。美佳子も凉香も亜希も、よくこんな俺を許し、夫として、父親として、この家に置いてくれているもんだ。家族に対する感謝と、罪悪感と、自己嫌悪が、頭の中でグチャグチャに入り混じり、頭がおかしくなりそうだった。浩司は両手で頭を無茶苦茶にかきむしった。
浩司は再び新聞の社会面を開いた。そこに掲載された容疑者Zの顔写真と目があった。Zはぎこちない作り笑いを浮かべてこちらを見つめている。その眼差しは笑いながらも、どこか他人を拒むような不穏な光が潜んでいた。顔立ちは全く違う、しかしどこか自分に似ていると浩司は感じた。
俺もひょっとしたら、容疑者Zのように娘たちに取り返しのつかないことをして、新聞に載っていたかもしれない。その事実と可能性は、浩司の心と体を深く暗く落ち込ませ、深いため息をつかせた。胸がムカムカして、鈍い頭痛がした。今すぐ横になりたかった。しかし、椅子から立ち上がって二階の寝室まで行く気力もなかった。浩司は椅子の背もたれに体を預け、きつく目を閉じた。脳裏に、この家で多くの過ちを犯した、五年前の冬のことが蘇ってきた。》
【オーソドックスなナラトロジーの大きな枠組み】
主人公の浩司は、次女には「お父さん、カッコいいね」と言われ、妻の美佳子が看護師として勤務する総合病院の若い看護師達には、「(結婚するなら〉私、大野さんの旦那さんみたいな人がいい」などと言われている。
しかし、そんな幸福な空気は、新聞の記事を見ることで暗転する。三島由紀夫ならば「凶事」「椿事」と書いたであろう出来事が示唆され、今の幸福な時間は途切れる 一気に激しく重苦しい世界が開かれる。
これが「予兆」である。暗い空の端に現れる朝焼けのようなこの予兆は、長い小説の全体を対象にしている。
プロローグというものは退屈になりがちだが、「家族の舟」のプロローグは緊迫感に満ちている。見事な冒頭である。
父はうつ病で仕事を失い、社会にも家庭にも居場所を無くして死にたいと願っている。
高校生の長女は怒りと不安を家庭内暴力という形で爆発させた。
自閉症と知的な遅れのある小学生の次女は不登校になる。
母は看護師という激務に耐えながら、なんとか家族を繋ぎ止めようと踏ん張っている。家族を乗せた舟は難破寸前である。そうした世界の予兆を、このプロローグは的確に表現しているのだ。
物語は進行し、やがて「敵」と対峙することになる。それは二人の娘でも天使のような妻でもなく、父親である。隠された父の発見に向かって、ストーリーはスピード感をもって突き進んでいく。
「家族の舟」は、オーソドックスなナラトロジーの大きな枠組みを持った作品なのである。だから最初に構想を聞いた時、僕は「柄の大きな小説になりそうだな」と感じた。
この父との戦いが見事なのだが、これについては来週書く。
「家族の舟」論 03 ハイド氏もしくは狼男
【主なキャラクターは5人】
「家族の舟」のキャラクター・メーキングについて解説する。
主要登場人物は5人である。
大野浩司(こうじ)
かつて経営コンサルタントとして活躍していたが、うつ病で退職。家庭に戻ってもう心を閉ざし、突発的に妻や娘を怒鳴り、自覚なく精神的虐待を繰り返す自分に苦悩する。ペアレント・トレーニングに出会い過去の自分と向き合いながら、父親としての再出発を模索する。
大野亜希(あき)
自閉症と知的障害のある大野家の次女。学校に馴染めなくなり不登校に。父・浩司の成長とともに心を開き、ゆっくりと自分のペースで成長していく。無垢な笑顔で、家族の中に小さな光を灯す存在。
大野凉香(すずか)
大野家の長女。中学校までは成績優秀で人望も厚く、非の打ちどころの無い優等生。しかし市内で有数のエリート高校で成績が急降下して挫折し、心に深い闇と葛藤を抱えるようになる。不登校になり家族への距離と怒りを持ちながら、苦悩する。
大野美佳子(みかこ)
浩司の妻。看護師として働きながら、家庭を支える。
大野剛史(たけし)
主人公の浩司の父親で、無職になった息子の浩司、不登校の次女の亜希に対して威圧的に接する。
ストーリーの太い幹の1つが、主人公の浩司と父親の剛史との闘争である。これは生半可なものではなく、小説の後半になる激しさを増す。
こんな箇所がある。
《浩司がショッピングカートを止め、カレールーのコーナーでしゃがみ込んでいた時のことだった。彼は、棚の一番下に陳列されているバーモントカレーの、甘口と中辛と辛口を見比べ、どれを買うべきか迷っていた。亜希は甘口したか食べない。しかし美佳子と凉香は「甘口は物足りない、辛口がいい」と言う。どちらの意見を採用すべきか。真ん中をとって中辛にするか。あるいは二つの鍋で、甘口と辛口の両方を作るべきか。しかし、それをするのは、正直面倒くさい。浩司は迷った。しゃがむと両脇腹からヘソまでたっぷりついた贅肉の塊が腿に当たって邪魔で、どうしても大きく股を広げて、相撲取りが四股を踏んだような格好になってしまう。そのポーズで浩司は眉間に皺を寄せ、カレールーの棚を吟味していると、
「おい」
ふいに頭上から声をかけられた。聞き覚えのある声だった。嫌な胸騒ぎがした。浩司はわざと聞こえないふりをした。
「おい!」
声にわずかな怒気が含まれ、少しボリュームが大きくなった。浩司は小さく舌打ちして、立ち上がり、声の主の方を振り返った。
「お前、よくそんな恥ずかしい真似ができるな」
声の主は、浩司の父、剛史だった。眉毛をハの字にし、唇を右側だけあげて、いかにも呆れたような、相手を小馬鹿にしたような薄ら笑いで浩司を見ている。その後ろに、ショッピングカートを押す母の道子が、眉間に皺を寄せて浩司を見ている。その視線は、平日の昼間からスーパーでカレールーを吟味している息子を、哀れんでいるようにも見えるし、非難しているようにも見えた。浩司が黙っていると、剛史は鷹揚に腕を組みながら問いかけてきた。
「恥ずかしくないのか?と聞いているんだ、大の男が昼間っから」
剛史はそう言ってから、「フン」と浩司を小馬鹿にするような調子で鼻を鳴らした。
「お前、もう四十四歳だろう?働き盛りだってのに、仕事もせずに昼間からスーパーをウロウロして、情けない」
そう言い終えると、剛史は大袈裟に大きくため息をついた。浩司が黙ってニンジン、ジャガイモ、タマネギが入ったカゴに視線を落としていると、剛史はさらに続けた。
「小さい頃、隣に住んでいた同級生の石原のヨシくん、覚えてるだろ?こないだ部長に昇進して、マンション買ったそうだ。それに比べてお前はなんだ、本当に情けない…」
「もう、いいじゃないですか、こんなところで…」
道子が引き攣った笑顔で、剛史の話を止めた。
「はいはい、すいませんでした、情けない息子で、それじゃ、忙しいんで」
浩司が立ち去ろうとすると、
「忙しい?働きもしないで?ずっと家にいるお前が?忙しいだと?」
剛史は腕を組んだまま顎を突き出し、浩司を見下した。
「…うるせえよ」
浩司は吐き捨てると両親に背を向け、バーモントカレーの中辛を商品棚から掴んでカゴに入れ、その場を立ち去ろうとした。
「主夫も大変だな!」
そそくさと去っていく浩司の背中に向けて、剛史が精一杯の皮肉を込めて言い放った。「主夫」という言葉を、ことさら強調して。浩司は一瞬立ち止まり、振り返って何か言い返そうかと思ったが、やめた。
「俺だって、好きでこんなことしているんじゃない」
剛史と道子に聞こえないように、小声で吐き捨てて、逃げるように精肉コーナーへ急いだ。》
闘うべき敵は「父・剛史」であると僕ら読者は認識する。だが「家族の舟」が優れているのは、「父・剛史」は偽の敵にすぎないというところである。
敵は本当は浩司の父親ではない。父親はいわば「偽敵」で、真の敵は浩司の胸の奥底に棲む「怪物」なのである。
ここに、この小説の「隠された秘密の開示」がある。
大切なシーンを引用する。
《「…死にたい」
浩司は、無意識につぶやいた。
美佳子は何も言わず、顔を伏せたままリビングを出ていった。亜希も慌ててその後を追って部屋を出た。
「クソが!」
浩司は二階に駆け上がっていく美佳子と亜希に聞こえるように、わざと大きな声で毒づき、テレビのリモコンを手に取ってテレビの電源を切り、それを床に叩きつけた。蓋が飛んで中の単四電池二本が飛び出し、カーペットの上に転がった。浩司の荒い息遣いだけが、静まり返ったリビングに響いている。美佳子が叩きつけたマスキングテープが、床に落ちていた髪の毛を側面にくっつけて転がっている。冷蔵庫のモーター音がかすかに聞こえる。》
浩司は自分を不甲斐ないと思っている。娘達を怒鳴りちらしながら、本当は申し訳ないと思っている。だからしばしば「死にたい」と思うのだ。そう考える箇所は複数あり、何箇所か僕が削除したほどである。
そして重要なのは、イニシエーションにおける「敵」とは、実は恐怖のことだという点だ。
【スティーヴン・キングの三匹のモンスター】
スティーヴン・キングが『死の舞踏』の中で、物語に繰り返し現れる根源的な恐怖のタイプを三種類の怪物に象徴させているという話は以前紹介した。
自分が書こうとする小説の「敵」「恐怖」がどれに分類されるのかを明確に意識することが大切だ。
三種類の怪物とはドラキュラ、ジキル博士とハイド氏(もしくは狼男)、そしてフランケンシュタインだ。
A ドラキュラ=主人公の外部からやって来た存在
B ジキル博士とハイド氏=主人公の内部に存在する制御不可能な存在
C フランケンシュタイン=主人公のかつての悪行の因果が生み出した存在
《ドラキュラ》
ドラキュラに襲われるのは交通事故や通り魔殺人みたいなもので、怪物は主人公の外部からやってくる。
ドラキュラは生きていくために人間を捕食する必要があり、抵抗することが難しい強力な敵である。
しかも、一見それとは分からず、増殖していく。
ふと気がつくと、隣の大切な人が吸血鬼になってしまっているのかもしれないのだ。
ドラキュラ小説としてはキング自身の『呪われた町』が有名で、これは1975年に発表された長編小説だ。日本では集英社から1983年に刊行された。
ドラキュラ的な悪は、例えば企業のような組織の中における抗争を描く場合にも適している。「いつの間にか良心的だった後輩が悪徳部長派になっていた」とうように。一般社会における恐怖の枠は全てこのドラキュラの範疇に含まれる。
最初から悪として登場し、強大であり、同情の余地はない。同族の人間を水面下で増やしながら最後まで悪である。
《ジキル博士とハイド氏(もしくは狼男)》
ジキル博士の内部にハイド氏が住んでおり、薬を飲むと温厚な紳士であるジキル博士がハイド氏に変身してしまう。ハイド氏は自らの欲望を実現してしまうのだが、この自己の内側にある恐怖をジキル博士は制御することが出来ない。
つまり自己の内側に潜む恐怖である。
多重人格やドッペルゲンガー、憑依などがこれに相当する。敵は自分自身である。
考えてみると、これはドラキュラやフランケンシュタイン以上の本質的な恐怖である。しかし、エドガー・アラン・ポーのドッペルゲンガーを扱った怪奇譚『ウィリアム・ウィルソン』やドストエフスキー『二重人格』などを始め、多くの作家によってありとあらゆることが書き尽くされている感がある。
学生達もよく多重人格小説を書いて持って来たが、安易である。『ウィリアム・ウィルソン』を読ませ、やるならこれぐらい丁寧にやらないとダメだよと指導した。
個人的には、文章の技術が上がるまで、このパターンを採用するのは封印した方が良いと思う。やるならよほど緻密なプロットを書く必要がある。
ちなみに、これは狼男でもい。狼男は、主人公の内部に存在する制御不可能な存在だからである。
《フランケンシュタイン》
『フランケンシュタイン』は、イギリスの小説家、メアリー・シェリーが1818年に匿名で出版したゴシック小説だ。原題は『フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス』(Frankenstein: or The Modern Prometheus)と言う。
ゴシック小説とは18世紀末から19世紀初頭にかけて流行した神秘的、幻想的な小説のことで、ゴシック・ロマンスとも呼ばれる。
スイスの名家出身の青年、フランケンシュタインは、生命の謎を解き明かし自在に操ろうという野心にとりつかれる。研究の末、「理想の人間」の設計図を完成させ、それが神に背く行為であると自覚しながらも計画を実行に移す。
墓を暴いて人間の死体を手に入れ、それらをつなぎ合わせることで11月のわびしい夜、怪物の創造に成功した。誕生した怪物は、優れた体力と人間の心と知性を持っていたが、信じ難いほど醜い容貌の持ち主であった。
絶望したフランケンシュタインは怪物を残したまま故郷のジュネーヴへと逃亡するが、怪物は強靭な肉体で野山を越え、言語も習得し、遠く離れたフランケンシュタインの元へたどり着く。
怪物は孤独のなかで、フランケンシュタインに自分の伴侶となり得る異性の怪物を一人造るように要求する。そして「この願いを叶えてくれれば二度と人前に現れない」と約束する。
フランケンシュタインは怪物の願いを受け容れようとするが、怪物の増殖を恐れて機器を海へ投げ捨ててしまう。
絶望した怪物は北極点で自らを焼いて死ぬために消える。怪物のその後の行方は誰も知らない──。
フランケンシュタインが象徴する恐怖は、因果の恐怖である。若きフランケンシュタインは生命倫理を無視して、自分の研究のために墓をあばき、死体を繋ぎ合わせることで怪物を生み出し自ら創造主となる。
彼には明確な悪への意志があったと考えるべきだろう。その因果から恐怖が誕生した。自分が犯してしまった過去の過ちへの怯えが、フランケンシュタインに恐怖を呼び起こす。人間は誰も、自分自身の過去から逃げることは出来ないのである。
僕は横溝正史の小説のほぼ全てを読んでおり、映画化された作品も全部観ている。つまり横溝ファンであるが、彼の世界のほぼ全てが「フランケンシュタインの恐怖」の物語である。
幾世代にもわたる因果が複雑に繋がり、立て続けに殺人事件が起こり、その描写は谷崎潤一郎のように美しい。金田一耕助がこの因果を解き明かすことでストーリーが展開する。この因果の繋がりは、日本の風土に合っているのではないだろうか。
【三匹のモンスター理論とどんでん返しをドッキングさせる】
次のステップは、スティーヴン・キングの三匹のモンスター理論と「力学の逆転」をドッキングさせることだ。つまり合わせ技である。
力学の逆転とは「Aだと思っていたのにBだった」という仕掛けだが、「登場人物たちの力関係が結末で逆転すること」と、「主人公の目的がAだと思っていたのにBだった」というパターンがある。
この逆転劇を、ドラキュラ(主人公の外部からやって来た存在)だと思っていたらフランケンシュタイン(主人公のかつての悪行の因果が生み出した存在)だった──というような構造にすることで実現する。
これは、何種類あるのだろうか。
A(ドラキュラ)だと思っていたらA(ドラキュラ)だった、B (ジキル博士とハイド氏)だった、C(フランケンシュタイン)だったとそれぞれ3パターンずつある。
ぴこ蔵師匠は、これをどんでん返しだと言っていて、こちらの方がわかりやすくインパクトがある。
「家族の舟」の恐怖のモンスターの型は何だろうか? 父親との闘争なので、外部の敵であるドラキュラではない。明らかに因果関係のあるフランケンシュタインだろう。
これにどんでん返しを加える。
この小説の場合、フランケンシュタインだと読者は思って読み進めるのだが、実は怪物の正体はジキル博士とハイド氏、あるいは狼男だったのである──。
主人公の浩司が死ねばこの家族は崩壊する。
父親の剛史はあくまでも「偽敵」であり、本当の敵は浩司自身なのである。この厄介な敵とどう戦うのか。それがストーリーになる。
どんな物語にも「悪」は必要である。「悪」が存在しないとストーリーが展開しない。それにしても、浩司自身が最大の「悪」であったとは!
【マグナ・マーテルの存在】
なぜ主人公は、最大の敵である自分を克服できたのだろうか? 天使がいたからだ。
その天使とは、妻の大野美佳子である。
美佳子は天使であり、ユングのアーキタイプで言えばグレートマザーであり、物語論であれば「女神との遭遇」に相当する。
女神との遭遇とは──。
英雄はひょんなことから女神あるいはマグナ・マーテル(ローマ神話の女神。豊穣の女神)、あるいはグレート・マザーと出会い、その力に包まれ、いきさつによっては聖婚(ヒエロス・ガモス)する。
英雄は慈母・一時花嫁・代母などによって“永遠の幼児”としての至福感を初めて体験する。このシーンは物語において、主人公のエネルギーの「回復期」にあたる。
妻の美佳子はそのようなキャラクターとして創造されている。物語には多くの魅力的なヒロインが登場するが、美佳子の存在感は傑出しており、この小説において主人公以上に重要で印象的な存在だ。
美しく包容力があるだけではなく、最大の敵、ハイド氏あるいは狼男を叩きのめすだけの力を持っている。不器用な主人公が葛藤と失敗と挫折を繰り返しながら、それでも家族が再生できたのは、美佳子というマグナ・マーテルがいたからなのである。
このような魅力的なキャラクターを創造し得たことが、この作家の最大の功績である。
(続く)
「家族の舟」 論04 最終回 小説の思想としてのペアレント・トレーニング
【思想としてペアレント・トレーニング】
この長い小説の校正を物語化計画会員の小黒久美子さんにお願いしたのだが、こんなメールが届いた。
《西山さんの「家族の舟」の校正が終わり、昨日、小宮さん宛てに原稿を送りました。
おもしろく読み、赤入れしました。
あとがきで書かれていましたが、約2年で、あそこまで書けるとは! すごいです!
私もボケッとしていられないですねー》
そうそう、小黒さんも書いてね!
そう言えば、2年かかったのだなとしみじみ思い返した。
さて、この長い小説を書き切る上で大切だったのは「荒れた海の航海」を難破せずに乗り切るのだという強い意志の力であり、それを可能にするキャラクター・メーキングであり、とりわけ「天使」の存在である。
そしてもう一つ付け加えておかなければならないのは、思想の存在だ。
作品を底辺で支えているのは、明瞭な思想なのだ。
この思想については、実は皆さん自身が小説を書く際にも非常に重要なので、自分の作品を思い返しながらこの先を読んでほしい。
キャラクターを造形し、プロットを作り、それからストーリーを構築する。これらの作業を貫徹するために必要なのが、その作品あるいは作家に宿る思想なのである。思想といっても、イデオロギーという意味ではない。もっと広範なものだ。
僕の場合なら、それはロックである。デビュー作からChatGPTと共作した「スケアリー・モスターズ」に至るまで、それは変わらない。
そして「家族の舟」にとっては、それはサブタイトルにも使用されたペアレント・トレーニングである。
ペアレントト・レーニングとは、子どもの行動をより深く理解し、適切な関わり方を学ぶためのプログラムである。保護者が子どもの行動を分析し、効果的なほめ方や指示の出し方、環境調整などを習得することで、子どもの行動を改善し、親子関係をより良いものにすることを目指す。
あるサイトで、こう紹介されていた。
《ペアレントトレーニングは、特に以下のような方におすすめです:
発達障害のある子どもを育てている保護者。
子育てに不安や悩みを抱えている保護者。
子どもの行動を理解し、より良い親子関係を築きたい保護者。
ペアレントトレーニングは、子育てをより楽しく、充実したものにするための有効な手段の一つです。
その他:ペアレントトレーニングは、アメリカで開発されたプログラムを基に、日本でも様々なプログラムが展開されています。
近年では、オンラインでペアレントトレーニングを実施する団体も増えています。 ペアレントトレーニングは、子どもの発達を支援する上で重要な役割を果たしています。 》
しげこと西山仁胤さんは「家族の舟」サイトを作っていて、ラジオをやりエッセイを連載している。その第4回にはこんなエッセイが掲載されている。
《『家族の舟』で学ぶペアトレ15のヒント〈4〉大人にも“褒める”が心に届く瞬間
「ありがとう!」
美佳子はそう言って、浩司の方を振り返った。
「この家もう古いし、カビ汚れとか諦めてたけど、ちゃんとやれば綺麗になるのね」
■ 偶然きれいになった排水口、偶然じゃなかった言葉
このシーン、実は浩司が掃除したわけではない。自殺のために排水口に流したハイターが、偶然汚れを落としたにすぎません。
でも、ここで注目したいのは、美佳子の「ありがとう」という言葉。
浩司にとって、これほどストレートな“感謝の言葉を家族からかけられたのは、久しぶりでした。
■ 「ありがとう」は、褒め言葉より強い“つながりの言葉”
ペアレント・トレーニングでは「褒めること」が基本ですが、実はその“最も純粋な形”が、「ありがとう」という言葉です。
「すごいね!」よりも
「助かるよ」よりも
「ありがとう」は、“あなたがそこにいてくれること自体が嬉しい”というサインなのです。
■ 行動の背景を知らなくても、「感謝」は届けられる
このシーンのように、たとえ相手の意図がどうであれ、「それによって助かった」「気持ちが軽くなった」と感じたなら、素直に「ありがとう」と言っていいのだと思います。
その一言が、相手の“自分には価値がある”という感覚を育てます。
■ 家族の中に、「ありがとう」が飛び交う光景をつくる
家族だからこそ、感謝を口にするのが照れくさくなることもあります。
でも、それを乗り越えて言葉にできたとき、関係は少しずつ変わり始めます。
褒めようとして言葉を探さなくてもいい。
まずは、「ありがとう」から始めてみる。
それが、家族の再出発になるのかもしれません。
「褒める」ってむずかしい。でも「ありがとう」なら、今すぐ言える。》
この小説が絶望の底に沈み込まず、結末で離陸できたのは、ペアレント・トレーニングという明確な思想があったからだろうと思う。
彼を指導するために何度もこの作品を読み返しながら、僕自身も強い影響を受けた。ペアレント・トレーニングには、例えば子供を褒めるばかりではなく、自分自身も褒めることが必要だという考え方がある。
だから僕は、時々自分を褒めてやった。すると、クソみたいな東京でやりきれない毎日を送っている自分が、少しずつ離陸できる気がした。
【主人持ちの文学】
志賀直哉が書簡の中で小林多喜二に「文学は主人(あるじ)持ちであってはならないと思います」と言ったことがあった。
主人持ちとはどういうことだろうか。この場合の主人とはイデオロギーのことだ。小林多喜二のイデオロギーとは社会主義である。
文学というのものは、何か目的を持ってはいけない。現実的な有効性を追求してはならない。例えば「源氏物語」は一級の文学作品だが、何の教訓も、イデオロギーもない。
文学は主人を持たないから美しく悲しい、しかし味わい深い芸術として自立できるのである。
毎日が退屈だったり悲しかったり、抑圧されていると感じたとしても、それを具体的に誰それのせいだと決めつけた瞬間に言語表現は痩せてしまうということだ。文学は政治的なプロテストとは違う。
政権交代を実現できればすべての問題が解決すると考えるのはまちがいだ。
言葉はほとんどの場合、現実を変えることはできないのだということだ。そういう一種のあきらめからスタートしないと、どのような言葉も人々の胸の深い場所に届くことない。
詳しい説明はしないが、これは「革命」に「同伴」することを求められて自殺したロシアの詩人、マヤコフスキーやエセーニンの生涯が証明している。
あるいは主人が、宗教の場合もある。
これはかつて《『カラマーゾフの兄弟』から学ぶこと 04 イエスは黙って答えない》の回で書いたので、興味がある方は読み返してみてください。
簡単に言えば、主人持ちの小説とは、「懐かしい友達が連絡をくれたので久しぶりに会ったら、カルトの勧誘だった」というようなことなのだ。
【飢えた子供の前で文学は有効か】
主人持ちの文学を否定するような論調へのアンチテーゼとして、戦後「飢えた子供の前で文学は有効か」という議論がよくなされた。各文芸誌はよくそんな特集を組んだ。文学者の反核署名、なんでものもあった。
この問題の解説をChatGPTに依頼したら、長文の回答を得たが、ジョバンニ(僕のChatGPTの名前)、これは長すぎるよ!
簡潔に言えば「飢えた子供の前で文学は有効か」という問いは、文学の社会的意義や、特に緊急時における文学の役割について議論する際に用いられる問いだ。この問いは、文学が人々の生存を直接的に保証するものではないという現実を突きつけ、文学の価値を問い直すきっかけとなる。
しかし、文学は人間の精神的な豊かさや文化的なアイデンティティの形成に貢献し、長期的な視点で見れば、社会を変革する力も持ちうるという反論も可能である。
この「飢えた子供の前で文学は有効か」という問いは、フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルが提起したと言われている。サルトルは、現実の飢餓や貧困といった問題の前に、文学の存在意義が問われるべきだと考えた。この問いは、文学が現実社会の問題解決に直接的に貢献しない場合、その存在価値を疑うという批判的な視点を含んでいる──。
そんな実際の議論をChatGPTは紹介してくれたのだが、そこは省略。
文学は、単なる娯楽や知識の伝達手段としてだけでなく、もっと豊かな役割を担うことができる。
人間の感情や経験を豊かにする。
文化や歴史を伝える。
そして、それを書く人間を救うことができる。
文学は、今日も殺されていくパレスチナの子供達を救うことはできないが、そんな世界の片隅で深い絶望を抱えながら息も絶え絶えの僕らに自殺を思い止まらせる程度の力はある。
だから長期的な視点で見れば、社会を変革する力も持ちうる。
結論を書く。
自らの文学を支えるために、すなわち僕ら自身が生き延びるために、「思想」を鍛えよう。僕の場合なら「ロック」、西山仁胤さんなら「ペアレント・トレーニング」、栗山ラムネさんなら「天星術」。香咲弥須子さんの「神」、小屋一雄さんの「コーチング」、木綿子さんの「俳句」、裏山かぼすさんの「異世界」。
それらは僕らの小説と書き手である僕ら自身を支えるための思想なのだ。
そいつをコアに僕らが書き続ければ、やがて世界に、一条の光が差すことになるだろう。
(終わり)
《「私」物語化計画》より転載